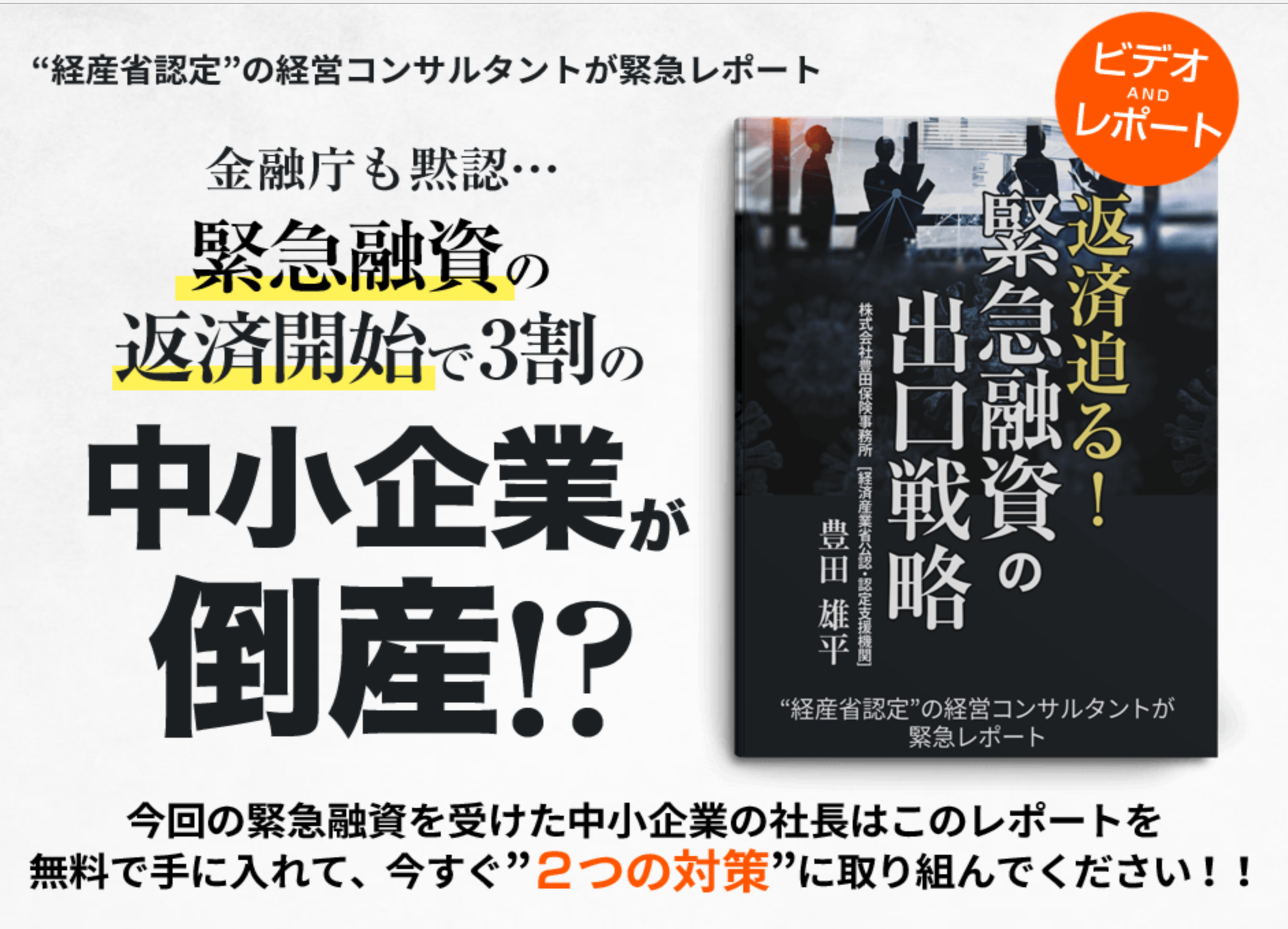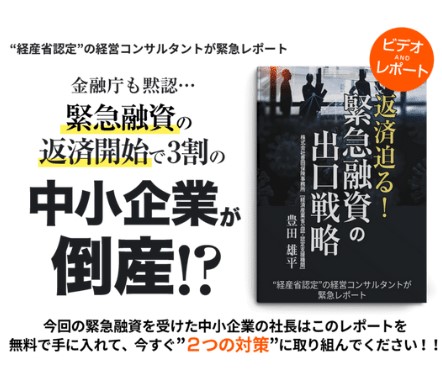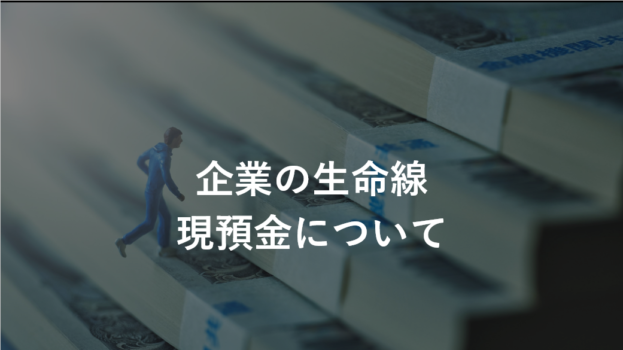
事業活動を行う企業は、現預金がある限り倒産することはありません。逆に、現預金が底をつけばその時点で資金繰りは破綻し、倒産することになります。
これは個人に置き換えても同じことです。収入を失っても、現預金があればしばらくは生活をすることができます。しかし、現預金が底をつけば生活を続けることはできなくなります。それほど現預金は大切なもので、事業活動を行う企業にとってもまさに生命線です。
それ故、銀行はこの現預金の動きを注視しています。そこで今回は「現預金」にフォーカスを当てた記事を作成しました。気になる方は続きをご覧ください。
目次
現預金は嘘をつかない
現預金は企業の損益状況を確認するうえでも大切なものです。世の中には決算書の粉飾が後を絶ちませんが、現預金は唯一といってよいほど嘘をつかない指標です。儲かれば基本的に現預金は増加します。
逆に赤字になれば現預金は減少する傾向になります。現預金は債務者の最終的な収益動向を把握するうえで、最も信頼度が高い数値なのです。
さらに現預金の水準を確認することにより債務者の資金繰り状況や今後の見込みを予想することができます。現預金水準が高い債務者は資金繰りにも問題が少ないものと考えることができます。
逆に、現預金水準が低い債務者はすでに資金繰りに問題がある、あるいはこれから問題が発生する懸念があるものと考えることができます。もっとも、現預金水準は業種や債務者の規模によって大小があります。一律の基準を明確に示すことは難しいですが、最低限年商の1か月分の現預金は望みたいところです。
このように信頼度の高く、企業の資金繰り状況を類推できる現預金については、貸借対照表を見たら必ず確認しましょう。そして1期だけではなく、数期間の現預金の推移を確認するようにしましょう。企業の真の利益状況や資金繰り状況を確認することができます。
資金繰り表で粉飾はバレる
現預金が増加傾向にある企業は、売上高や借入金などほかの指標との関係もありますが、概して業績が順調で資金繰りの懸念が少ない企業だと考えることができます。逆に現預金の水準が年々低下している場合には、資金繰りがタイトで追加の融資を受けないと資金繰りが維持できない可能性が高いと考えることができます。
当然、返済原資が乏しくなることも考えられ、債務者区分の判定にも影響が出てくる可能性が高くなります。
損益計算書で見る限り毎期安定的に黒字を計上しているにもかかわらず、現預金が減少している場合には、もしかしたら決算書を粉飾しているかもしれません。なぜなら、儲かっていればそれに比例して現預金も増加するのが自然だからです。
このように現預金は、企業の実態を示す最も信頼度が高い指標です。数期間の推移を検証することで、企業の実態を類推することが可能となります。