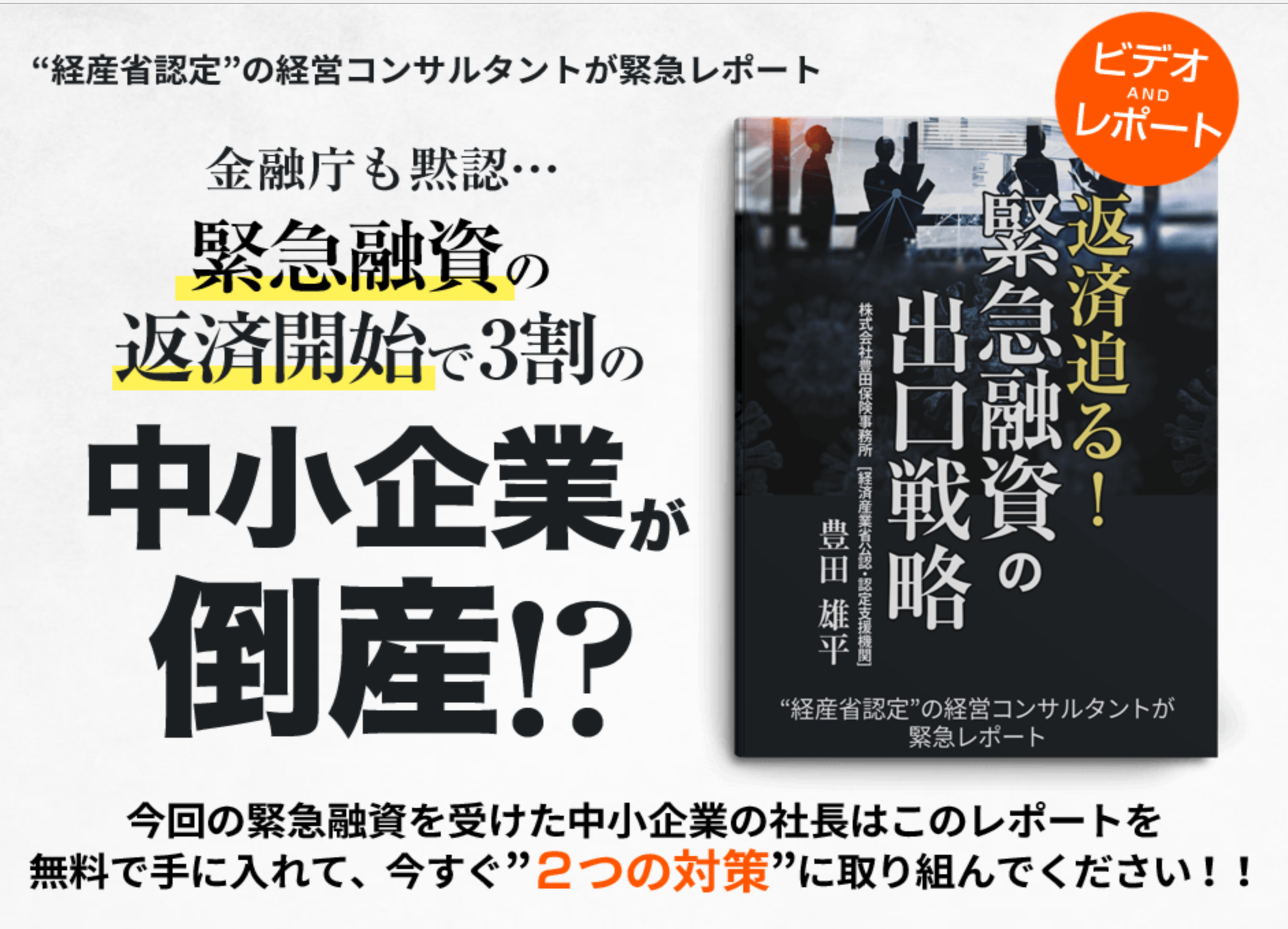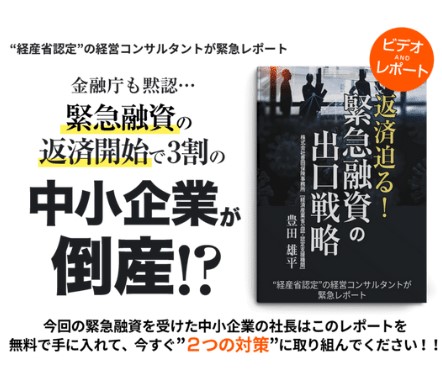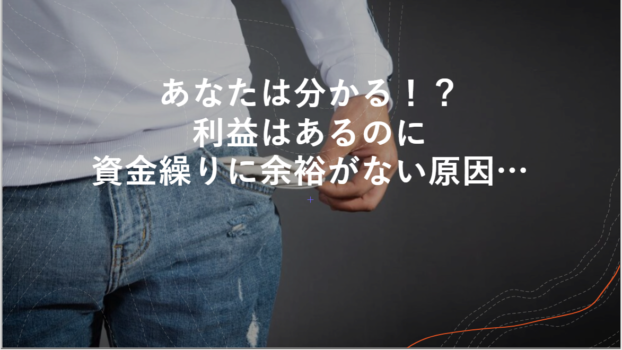
鉄鋼業を営んでいるA社。最近になって急に資金繰りに余裕が無くなってきたと感じています。売り上げは以前より下がりましたが、赤字になるまでは落ち込んではいません。
しかし、黒字であるにもかかわらず、ほとんどお金が手元に残らない状態なのです。むしろ最近ではお金が不足がちで、月末には手形を割り引くなどして支払いに対応している・・・そんな状況です。
なぜ、利益が出ているにもかかわらず手元にお金が残らないのかが知りたいと悩んでいます。
あなたはこの悩みに対して明確な答えを出すことができますか?もしできなければ、今回の記事はあなたの資金繰りに対する知見を拡げる大きなきっかけとなることでしょう。ぜひ続きをご覧ください。
目次
A社のような悩みを抱える会社はたくさん存在する
A社の質問のポイントは、利益が出ているのになぜ、手元にお金が残らないのかということです。ずっと右肩上がりの好景気の時代では、毎期売り上げが拡大し多くの利益と現金が手元に残っていました。
ところが経済が悪化し不景気になると、A社のように実際に利益を計上しているにもかかわらず、手元には全くお金が残らないという会社がたくさん存在します。
もっとも重要なことは、いくら利益を計上していても、お金が不足すればあっという間に倒産してしまうという事です。たとえ1円の支払手形でも期日に決済することが出来ない、すなわち手形の不渡りを出してしまったらアウトです。
不渡りを2回出してしまうと、銀行取引が停止されてしまいます。そうすると会社は資金調達がほとんど不可能となり、最終的には倒産へと向かうことになります。
なぜ利益が出ているにもかかわらず、お金が不足してしまうのでしょうか?
すべてはタイムラグから
倒産した会社の決算書を見ると、全て赤字会社かというとそうではありません。利益を計上していても、多くの会社が倒産しているのです。会社はどんなに利益を計上していても、お金の流れがストップしてしまえばその時点で倒産したも同然なのです。
皆さんの中には黒字で利益を出している会社が倒産するなんて…と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。おそらく利益の多い会社は資金も豊富なはずだから、お金が不足することはないだろうと思われるはずです。
しかしここで一つの誤解が生じています。それは利益が多いからといって、必ずしもそれだけのお金が手元にあるとは限らないという事です。その原因は一言で言えば、 タイムラグ=時間のズレ です。
一昔前の会社の商売の形態というのは、通常商品を販売すると、商品の引き渡しと同時に現金も受け取る現金主義が主流でした。会計用語でいう所の現金主義というものです。
つまり「売上」の時期とお金の「回収」の時期が一致していたのです。現金主義の場合においては資金繰りについてそれほど頭を悩ますことはありませんでした。
ところが現在は信用経済の時代です。原材料を購入したり、商品を仕入れたりした場合の決済方法は小売業以外では掛けによるのが一般的です。
会計の世界では、損益を計算する場合には原則として発生主義により処理することとされています。発生主義とはお金の出入りとは関係なく、収益と費用の「発生」に基づいて損益計算をする方法です。
発生主義によれば、商品の仕入れを掛けであろうが現金であろうが関係なく、「仕入」という事実があれば費用として認識されます。逆に会社が商品を売り上げれば、たとえその回収が手形であろうが現金であろうが、掛けで売り上げようが「売上」という事実があれば、収益として認識されます。
このように発生主義から計上された収益から、費用を差し引いた残りが利益になります。
つまり損益計算が、
|
利益=収益―費用 |
として計算されるのに対し、お金の流れ、すなわち収支計算は実際にお金が動いたときに、
|
収支=収入―支出 |
と、計算されることになります。
利益を計算する場合に、実際のお金の動きは関係ないのですから、こうして計算された利益についても当然現金の裏付けはありません。
通常は売り上げによる代金回収よりも、仕入や販売などの支払いのほうが先行するので、どうしてもお金が不足になりがちです。これで利益が多く出ている会社は、お金も沢山あるということには必ずしもならないことがお分かりいただけたと思います。
勘定合って銭足らず
「勘定合って銭足らず」とは、とりあえず利益が出ているにもかかわらず、手元にはお金が残っていないという状態をいいます。ここでいう「勘定」とは利益のことで、「銭」とはまさにお金のことを指しますが、先程の現金主義であれば「勘定合って銭足らず」の状態にはなりません。
あくまで現代の信用経済の下で、発生主義により会計処理が行われると、「勘定」は合うのに「銭」が足らなくなるのです。