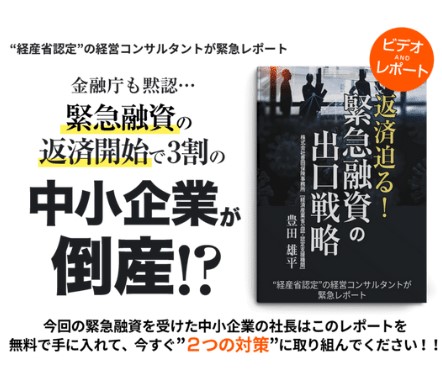「小規模宅地の特例」というものをご存知でしょうか?
例えば相続後、両親が住んでいた自宅に長男が住むとします。実はこれだけで土地の評価を80%減らすことができるのです。
目次
どんな場合に適用されるのか?
例えば、お母さんが亡くなったとします。そこに住んでいた自宅に同居の次男がそのまま住むといった場合です。
次男からすると、「今も昔も自分が住んでいるのに、親が亡くなっただけでなぜ税金を払うんだ!」という話しになってきます。
なので、ここの土地に関しては評価を8割カットしていいですよ、ということです。
仮に、その土地が1億円の評価だとすると、1億円に対して税金がかけられる話が8割カットですから、評価は2,000万円までダウン。
この特例を使うだけで相続税の基礎控除内に収まることも多く、非常に効果が大きいことが分かります。
特に、財産は実家の土地と建物がほとんどで、現金なんかはほとんどない!という家庭には、かなり効果が大きい特例なのです。
事業用の土地にも適用できる?
例えばお父さんがご商売されていたとします。その商売を長男が継ぐといった場合、事業用に使っている個人の土地を後継者が継ぐのであれば、これまたこの特例を適用することができます。
その他、駐車場や賃貸業(貸家やアパート経営)を営んでいる土地についてもこの特例を適用することも可能です。
適用される土地の面積に上限がある?
事業用や居住用のために手離せないからといっても、そんなに大きな面積についてまで援助する必要はないという考え方から、この特例によって減額してもらえる部分というものに上限が決められています。
その上限は、
・居住用宅地…330㎡ ・事業用宅地…400㎡ です。
居住用については、平成26年までは240㎡だったのですが、税制改正により平成27年1月1日より330㎡に拡大され、より大きな恩恵を受けることができるようになりました。
このように、この特例は上限が面積によって設けられていることから、適用を受けることができる宅地が複数ある場合には、なるべく単価の高い土地から適用を受けると減額できる金額が大きくなります。
効果は大きいが注意点も!
この特例、メリットは大きいのですが、「争う族問題」に注意が必要です。
どういうことかと言うと、税金を計算する時にはこの制度を使って8割減で土地の評価を計算していいのですが、問題は財産の分け方を検討する時。
分ける時は8割カットした状態の金額で平等を図るのではなく、元の金額で分けないと平等じゃないのです。
仮に子供が2人残されたとして、相続税の申告は・・・
自宅の土地が本来は1億円のところ、小規模宅地の特例を使って2,000万円に減額。
自宅の建物は1000万円でその他の財産は現金が1,000万円。
結果、相続財産は合計4000万円。
この場合、基礎控除の範囲内ですので相続税を支払う必要はありません。
しかし分割の時は土地が1億円、建物1000万円、現金が1000万円の合計1億2000万円、これを基本として分割の話し合いをしなければいけないのです。
法律では兄弟で平等に半分ずつですから、これでは平等に分けることはできません。
節税ばかりに注目するのではなく、家族間の争いが起きないように注意したいものです。