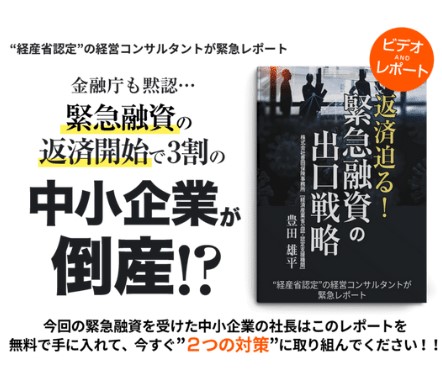事業承継には、「誰に」「いつ」「どのようにして」株を渡すのか?という所が非常に重要になってきます。
そして「誰」の部分が子供なのか?社員なのか?第三者のなのか?で対策は変わってきます。
そして必ずしも承継出来るわけではないことも忘れてはいけません。
それぞれの観点で何がポイントで重要になってくるのか?解説します。
目次
1つ目.子どもに承継するケース
これはまず、後継者に経営者としてのまず適正があるのか。
経営者として向いているのか。
社員から信任が厚いのか。
そもそも息子が、自分の親が一生懸命やって苦労している所を見てきた中で、会社を引き継ぐ意欲があるのか。
このあたりのマインドの部分が結構大事なポイントになってきます。
さらに社内に後継者の兄弟がいる。
おじさん、おばさん、父親の弟が専務でまだ社内に籍を置いているという状況だと、「若造のお前が何を言う!」という感じで経営がやりにくいということにもなりがちです。
そんな中で後継者に経営権を集中させることができるかどうか。
この辺りが極めて難しいポイントになってくることがあります。
息子が本当にこの会社を引き継いでくれるかどうか、意志固めをしてくれるかどうか。
その上で適正があるかというところを見極めていきながら、株の移転を考えていく。
ここを疎かにすると、「株は渡したが、経営なんか自分にはできない!」と、放り出す形になれば、元の木阿弥になってしまいます。
その部分で、後継者というものは社内、社外の様々な目がある中で、先代から引き継ぐプレッシャー、こういうものにどう向き合っていくか。
しっかり見ていく必要があるのです。
2つ目.経営幹部に承継させるケース
この場合はまず、経営者として人望や能力があるのか。
ここで言う経営者としての能力というのは、実務はキチンとこなせる幹部社員だが、こと経営の部分になった際、本当に経営の目線でものが見れるかどうか。ここがポイントになってきます。
例え「このよくやってくれる部長に任せたい」と思ったとしても、後継候補者である部長にそれを告げた瞬間、「そんな、滅相もない!勘弁してください!」と言う場合も考えられます。
肩に乗る責任、重責に堪えられるかどうかということも十分に判断する必要があります。本人が本当にやる気を持って覚悟を決めてくれるかどうか。
この辺りをしっかり押さえておく必要があるのです。
また、場合によっては会社の株価が億単位になっていた場合です。
経営幹部に「会社を引き継ぐために会社の株を買い取ってくれ」と言った場合、この経営幹部が今までの報酬からの蓄えで、株を買い取れるまでの資金があるのかという問題が発生します。
この場合、そのようなお金は持ち合わせていないことがほとんどでしょう。
このような中で、次期承継者である自身の子供が育つ間までのワンポイントの承継なのか、完全承継なのか。ここの部分もかなり大事なポイントになってくるのです。
さらに経営幹部に承継させるケースでいうと、自分の子どもがまだ若く、ある程度成長するまでの間、例えば「10年~15年、子供が成長するまでの間を承継してもらえれば・・・」というケースであれば、幹部社員に持株を持たせずに、オーナー家が持株を持ち続けるということもできます。
また、承継者が自身の子どもではない場合、つまり完全承継という形で親族以外の経営幹部に任せるというのであれば、オーナー家が持ち株を持ち続けるようなことはせずに、株も含めて全部渡す。このような形にしていく場合もありします。
いずれにしても、この次期の承継者に対してはしっかり時間をかけて承継について細部の合意を取り付けていく必要があるのです。
3つ目のポイント、M&A
M&Aとはすなわち、「第三者に承継する場合のポイント」になります。
雇用を継続してくれるのか。不慣れな会社の売却の中で条件が上手く合うのか。
そもそも、M&Aしてくれる企業をどこから見つけてくるのか。
このような問題、ポイントがあります。
雇用や売買の条件、更にはこれまでの経営方針や企業文化まで引き継いでもらえるのか。
こういった所も交渉の中では大事になってきます。
経営方針や企業文化まで引き継がれるまでの間、売却後も一定期間雇われ社長として、現オーナーがこの会社を見届ける。
ある程度の企業文化が根付けたという段階で完全に退く・・・
このようなケースもあったりします。
売却先との条件など、不慣れな交渉をどのようにまとめていくか。この辺りについては、M&Aの専門家をしっかり探していくということも大事になってきます。
最後、清算・廃業
まずは清算・廃業の件数の推移ですが、答えから言うと、「増加の一途を辿っている」ということが言えます。なぜなら、倒産した件数が2017年で約8500件に対し、廃業した会の数が約2万4千件にも上っているのです。
多くの場合、倒産の件数の方が廃業の件数を多く上回っているのでは?と考えがちです。
しかし、実態は高度成長終わった後、高齢化した経営者の抱える大きな問題としてこの事業承継の問題を抱えているということが分かります。
そして最終的には、会社はある程度、それなりに大きくなったが、後継者がいないことで廃業せざるを得ないという結果になってしまっているのです。
それが倒産件数の2.8倍の件数で中小企業が廃業しているという実態があるのです。
そういう意味から言っても、高齢になればなるほど、事業承継の選択肢というのが限られてくる。だからこそ早い段階で、承継についての検討及び対策というものをしっかり考えておく必要があるのです。
このままでは、日本のモノつくりが衰退し、経済自体も衰退してしまいます。
そのようなことを起こさせないためにも、事業をどのように承継していくのか?しっかりと考えたいものです。