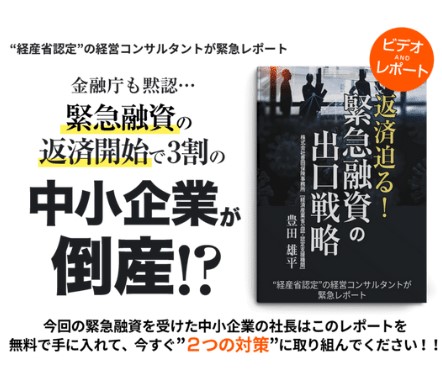前回(銀行格付けのよくある勘違いその1)の続きです。
今回でラストになります。前回の記事を見ていない方は、併せてご覧になられてください。
これでもう、あなたは銀行格付けについて色んな情報に惑わされなくて済むはずです。
目次
銀行の格付け(自己査定)は定量・定性評価と潜在返済能力の3段階
「定量評価で点数の低い会社は定性評価でランクアップされる可能性は低い」
近年、事業性評価を金融庁が提言したことで、似非コンサルタントが2次評価である定性評価をあげることで格付けをランクアップさせることができると言っています。
ハッキリと伝えておきますが、このようなことはほとんどありません。
銀行の格付けは定量評価(一時査定)と定性評価(二次査定)、潜在返済能力(三時査定)の3段階で構成されています。
定量評価(一時査定)は決算書の中身の評価ですが、ここで点数が悪ければ、定性評価(二次査定)でランクアップされる可能性は限りなく低いのです。
銀行員は経営コンサルタントではありません。
お客様のお金を集め、預金していただいたうちの6~7割を、個人の住宅ローンや会社に融資します。あくまで本業はお金を貸すことです。
彼らが決算書を解読することができ、財務コンサルタントとしての能力を身に付けていれば、融資したくてもできなくなる会社が増えてしまうでしょう。
定性評価(二次査定)とは目利き力のことです。なぜなら定性評価の中身は「市場動向」、「景気感応度」、「市場規模」、「競合状態」以下さまざまな項目があります。
このような項目の確認を今の銀行員があなたの会社で行っていますか?
今の銀行員はやることが多すぎてこのような確認をすることはほとんど無理だと言って過言ではないでしょう。
融資先の会社へ行き、定性評価の項目を見せ、融資時や定期的に決算書を提出した時期に確認しているか聞いても、確認していないというでしょう。
決算書の基準と違い、明確な基準がないため、論拠もないのです。
当然ですが、業績が悪い会社の経営者の能力が高いかと言えば、そうではないでしょう。
結局、因果関係の過程が定量評価として出ているため、決算書の内容が良ければ定性評価の点数を高くつても文句は言われません。
業績が悪い会社も因果関係があるため、定性評価を良くしてしまったら金融庁から指摘があります。銀行がそのようなことをするはずがないため、定性評価でランクが上がるということは夢物語であることが言えます。
営業利益・経常利益が2期連続で赤字を計上した時
よく、営業利益・経常利益が2期連続で赤字を計上してしまうと今後の融資が厳しくなると言われます。
これは果たして本当なのでしょうか?結論から言うと、
「代表者の個人収支・資産余力が相当額あれば普通に融資を受けられる」です。
たとえ2期連続で営業利益や経常利益が赤字であったとしても、潜在返済能力として代表者個人の個人収支・資産余力が相当額あれば、正常先の企業に該当して普通に融資を受けている企業もあります。
2年連続で本業の儲けである営業利益、または企業の総合力といわれている経常利益が赤字になってしまうと、なかなか新規融資を受けられません。
返済能力が低いとみなされる可能性が高いからです。
しかし、そのような会社であっても、第3次評価である「潜在返済能力」が高い場合、融資を受けられる可能性があります。
審査の基準となるのは、代表者の個人収支、生活実態、役員報酬の額、世帯構成(人数、年齢、教育状態)です。ここから生活費を紐解きます。
年間2,000万円の役員報酬であれば、税金や社保を差し引いた手残りはおおよそ1,200万円ほどでしょう。
そうすると毎月100万円の手取となります。その中で半分の600万円で生活しているとなると、残りの600万円は経常利益に加算してもいいのではないかという判断です。
いざという時に、連帯保証人となっている社長が個人の資産を取り崩してでも銀行融資を返済してくれる。このように判断されます。すなわち、社長個人の資産を適切に評価してくれているということです。
自己査定(銀行の格付け)は決算書をそのまま評価していない
上に述べたように、自己査定は企業と代表者の実態のバランスを確認しているため、決算書をそのまま評価しておらず、代表者の資産背景や役員報酬を含めた形で評価しています。
決して決算書を評価していないわけではありません。
社長の個人収支や資産背景を加味したうえで会社の資産を時価で引き直して実態がどうなのか?という所で判断しています。
この感覚は銀行員は教育を受けているため理解できますが、外部の人間は最初はなかなか理解することが難しいことでしょう。