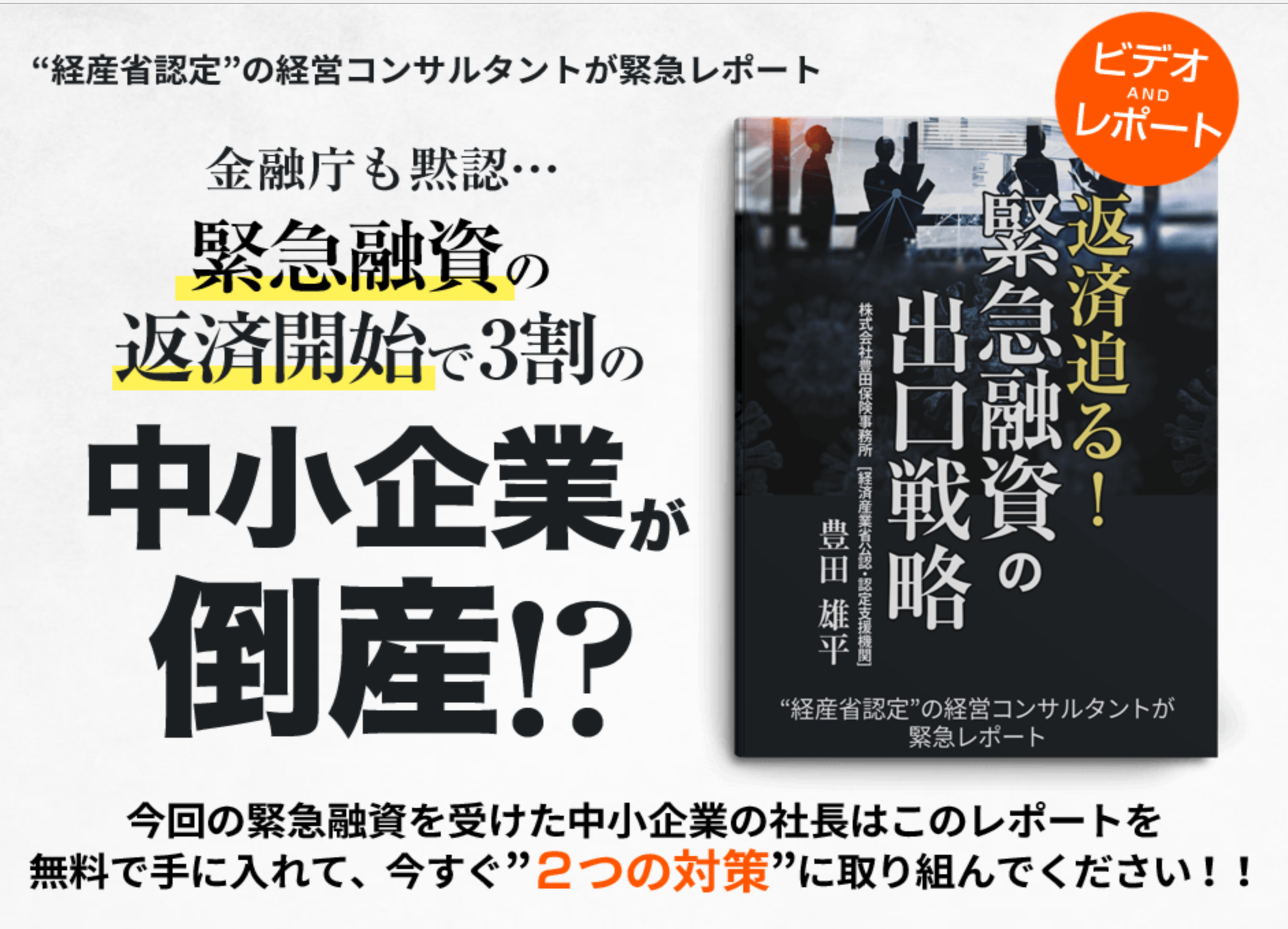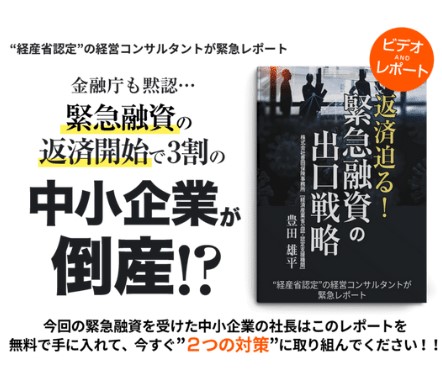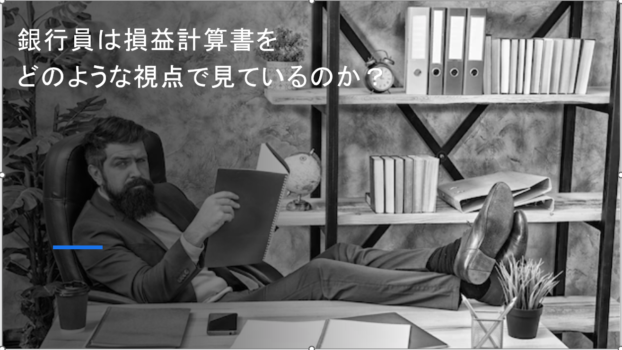
これまでに銀行格付について何度かお伝えしてきましたが、銀行員が損益計算書をどのようなことに注視しているのか?このような1つの財務諸表にフォーカスを置いたものはこれまでお伝えしてきませんでした。
銀行格付で言うと、損益計算書の重要指標は営業利益と経常利益です。しかし損益計算書には売上高を始めとし、企業の状況を分析するためには切っても切り離せないものがあります。
そこで今回は銀行員が損益計算書をどのように見ているのかについてお伝えしていこうと思います。(内容が長くなるため2部構成でお伝えします。)
目次
損益計算書における判定のポイントその1 売上高の推移
債務者の状況を把握するうえで、まず確認したい点は売上高の推移です。
売上は債務者の事業活動の源泉であり、かつ出発点です。売上が立たなければ事業活動は成り立ちません。皆さんの場合で考えてみると、収入がなければ生活ができません。預貯金があればそれを取り崩すことで一定期間生活はできますが、預貯金が底をつけばもう生活はできません。同じことが事業を営む企業や自営業者にもあてはまるのです。
売上高の推移そのものは債務者区分(銀行格付)の判定項目ではありませんが、判定にあたって債務者(企業)の状況を大局的に見ることがとても大切であり、売上高の推移を見ることによって、債務者の今後の動向を判断することになります。単に前期に比べて「増えた、減った」を確認するだけでは意味がありません。
少なくとも5年間、できれば10年間での長期のトレンドを確認してほしいのです。長期のトレンドを見て売上が増加しているのであれば、債務者は成長過程にあることが見込まれますし、基本的には前向きに融資等を検討することができます。
一方で、今期の売上は前期比プラスであっても、長期のトレンドで見ると売上が減少している場合には、事業が衰退傾向にあることが懸念されます。このような場合には、事業の回復可能性を検証する必要が出てきます。
冒頭でも述べましたが、売上高というのは債務者の事業活動の源泉であり出発点です。少し大げさな言い方かもしれませんが、売上高の推移を長期のトレンドで捉えることで債務者の将来性を推測することができます。売上が低下傾向で事業の衰退が懸念されるにもかかわらず、前期と比べて売り上げが増加していることだけにとらわれてしまうと、債務者の実態把握を誤ることになります。
売上高の推移を長期のトレンドで捉えることにより、よりしっかりとした融資判断が可能となり、的確な融資推進の可能性が高まります。また売上高が減少している債務者に対しては、経営者に今後の対策等のアドバイスを行うことが求められます。
損益計算書における判定のポイントその2 そもそも黒字か赤字か
債務者の状況を分析する際、まずは大局的に債務者の状況を捉えることが大切です。いきなり細部にこだわり、例えば各種財務指標の数値を分析しても債務者の全体の状況を捉えることができません。
債務者の本来の姿を誤って把握してしまい、正しく債務者区分を判定できない可能性もあります。最初にざっと決算書類を眺めて、債務者の全体像を自分なりに把握するのです。そして全体的なイメージを持って各種分析に入っていくと、それぞれの数値等の意味するところが理解しやすくなるはずです。
損益計算書は債務者の収益状況が記載されている書類ですが、まずはそもそも黒字なのか赤字なのかを確認してみましょう。儲かったのか、儲からなかったのかをざっと把握するのです。
融資業務においては、新たな融資を実行することはもちろん大切ですが、融資した資金をきちんと回収することもとても重要です。そして融資の返済原資は最終的には収益です。黒字であれば一応は返済能力が認められ、一定の返済原資を債務者は持っていることになります。逆に赤字であれば返済能力が認められず、返済原資を持っていないことになります。
また、黒字か赤字かは1期だけで判断するのではなく、なるべく長期間の推移で把握するようにしましょう。長期間にわたり黒字決算であれば、債務者は安定的に収益を上げられる、つまり儲けられる体質であり、融資の返済能力が安定的に認められる債務者だと考えられます。
逆に長期間にわたって赤字が続いている場合には、債務者は赤字体質で注意を要する先である可能性が高くなります。融資の返済能力がない、あるいは乏しい債務者ということになり、融資の回収が最後まで可能なのかどうかを見極める必要が出てきます。債務者をどのように支援していくのかを考える必要も出てきます。
もっとも、黒字であればそれで良いということではありません。黒字といっても金額が数十万円とか数万円であれば、返済能力はほとんど認められない可能性が高いですから、安心することはできません。
一方で赤字であれば、毎期続いているのか、今期だけ赤字なのか、後から述べるようにどの段階で、つまり営業利益の段階で赤字なのか、経常利益の段階で赤字なのか、税引前当期純利益の段階で赤字なのかを把握しましょう。
ただ、いずれにしても赤字であれば要注意です。なぜなら、先ほども述べたように融資を返済する能力が乏しいからです。債務者に対しては、なぜ赤字なのかの把握を含めて、今後の動向に十分注意を要することになります。