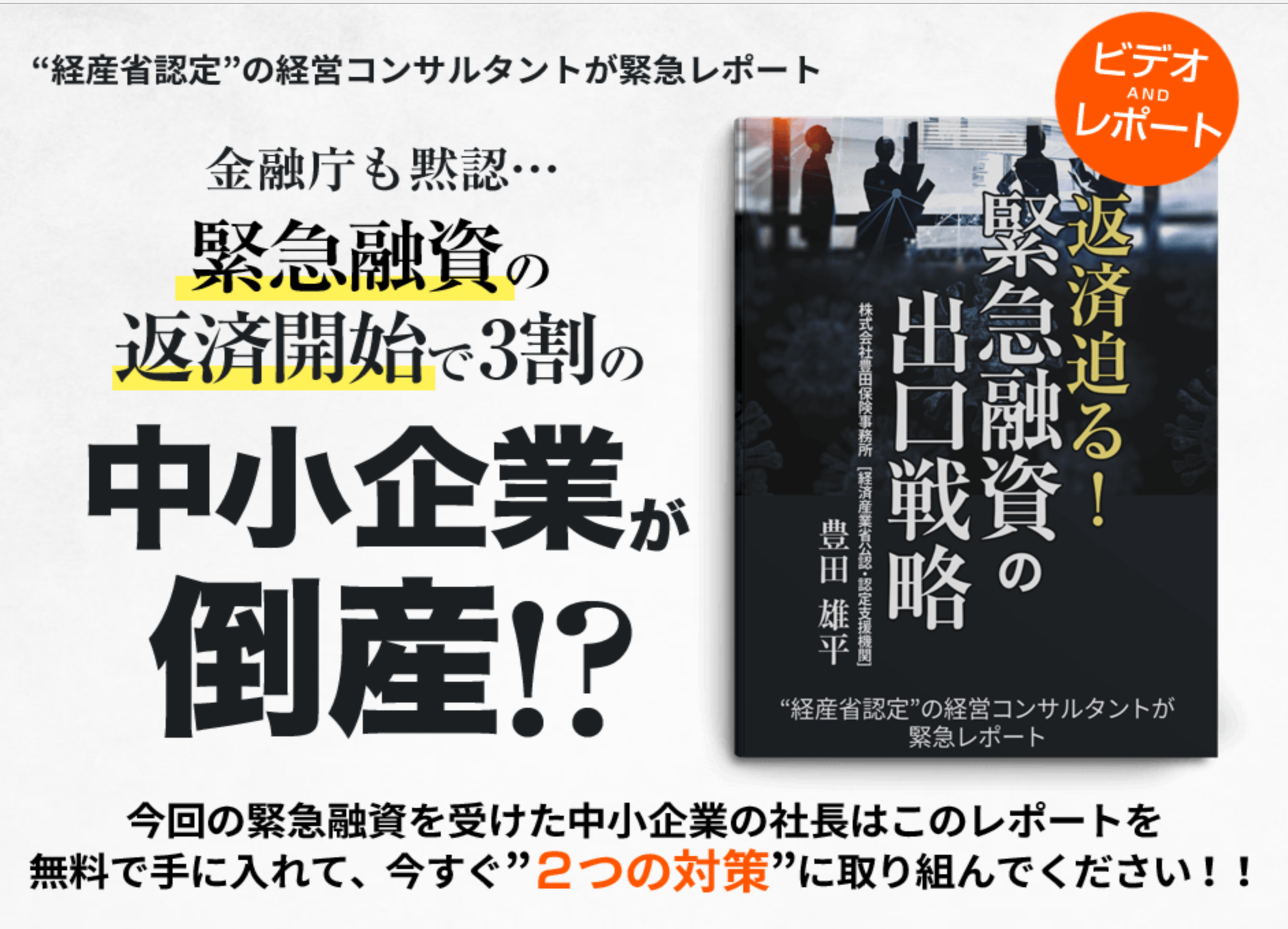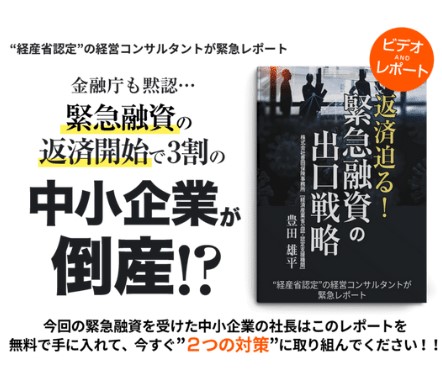融資を受ければ、経営者は個人保証として連帯保証を求められます。それに伴い、多くの経営者は会社の連帯保証人となっているのが現状です。
またこの連帯保証が事業承継時に大きなボトルネックとなり、円滑な承継の妨げとなっていることも事実です。近年、「経営者保証のガイドライン」の発行を機に、次第に連帯保証を求めない動きもみられる中、こちらのガイドラインには法的拘束力がないため、十分に機能しているとも言い難い状況です。
そこで今回は、「銀行の選択」・「生命保険」を活用した連帯保証解除の方法についてお伝えしていきたいと思います。
目次
年商規模にあった銀行の選択をもとに連帯保証を解除する
① 融資の少数取引は絶対にしない
メインバンクを持つことはよいことですが、年商規模に応じた「銀行の選択」を行うことは重要なことです。ちなみに年商規模に応じた銀行の選択は次の通りです。
| 年商1億円以内 | 2~3行 |
| 年商1億円~3億円 | 3~4行 |
| 年商3億円~7億円 | 4~5行 |
| 年商7億円~10億円 | 5~7行 |
| 年商10億円以上 | 7~9行 |
このように企業規模により取引すべき銀行の数が変わります。
また年商規模が大きいのに取引銀行数が少ないと、メインバンクの「言われるがまま」の取引となる可能性が高くなり旧経営者の連帯保証も外せなくなる可能性があるので注意が必要です。
② 融資取引をしている銀行から自社の融資方針の確認を行う
銀行によって企業の格付が同じだとしても融資スタンスは微妙に変わります。また銀行の規模や銀行の財務状況で格付や融資スタンスも異なります。
そのため金利で銀行の選択は行わないようにするのが賢明です。多少金利が高くても自社の融資スタンスのイメージを提案してくれる銀行と取引を行ったほうが得策と言えます。
③ 旧政府系の金融機関との取引を考える
商工中金・日本政策金融公庫はコンサル能力も高く、旧政府系の金融機関と取引を行っていると市中金融機関も安心します。
生命保険で連帯保証を解除する
① 解約返戻金の残高証明を活用する
決算書を銀行に提出するときに、決算時点での解約返戻金相当額の残高証明書を生命保険会社から取得し、銀行に含み益があることをアピールしていく方法があります。
銀行も数年前から生命保険の取り扱いを開始しましたが、保険税務は難しく、理解しているようで理解できていません。
そのため、貸借対照表上で含み益があることをアピールして実質自己資本比率が高いことを銀行員に伝えるようにすると良いでしょう。
② 個人で加入の生命保険も活用する
個人の生命保険についても決算時点での解約返戻金相当額の残高証明書を取得して銀行に報告してみてください。
銀行は経営者の資産背景の確認をするように教育されています(銀行格付第3次評価)が、実態は事項の預金取引や一部の所有不動産情報しか把握していないと言われています。
そのため実態を銀行に伝え、個人資産が潤沢にあり、会社の業況が悪くても返済は間違いないことをアピールするようにすると良いでしょう。
※ここは非常に重要なポイントです。過去記事、赤字でも債務超過でも銀行が融資を行う企業とは!?で詳細お伝えしていますので併せてご覧ください。
③ 解約も1つの手段
生命保険は目的別で加入していると思いますがケースによっては貯蓄性の高い生命保険のすべてを解約し、財務指標の改善をしていくことも視野に入れておいてください。
銀行は経営者保障以外でも総合的に考えて判断をしています。そのため含み益でアピールしても響かない銀行も当然存在します。その場合、協議のうえ貯蓄性の高い生命保険を解約し、銀行融資の一部返済を行う旨、銀行へ相談してみるとよいでしょう。