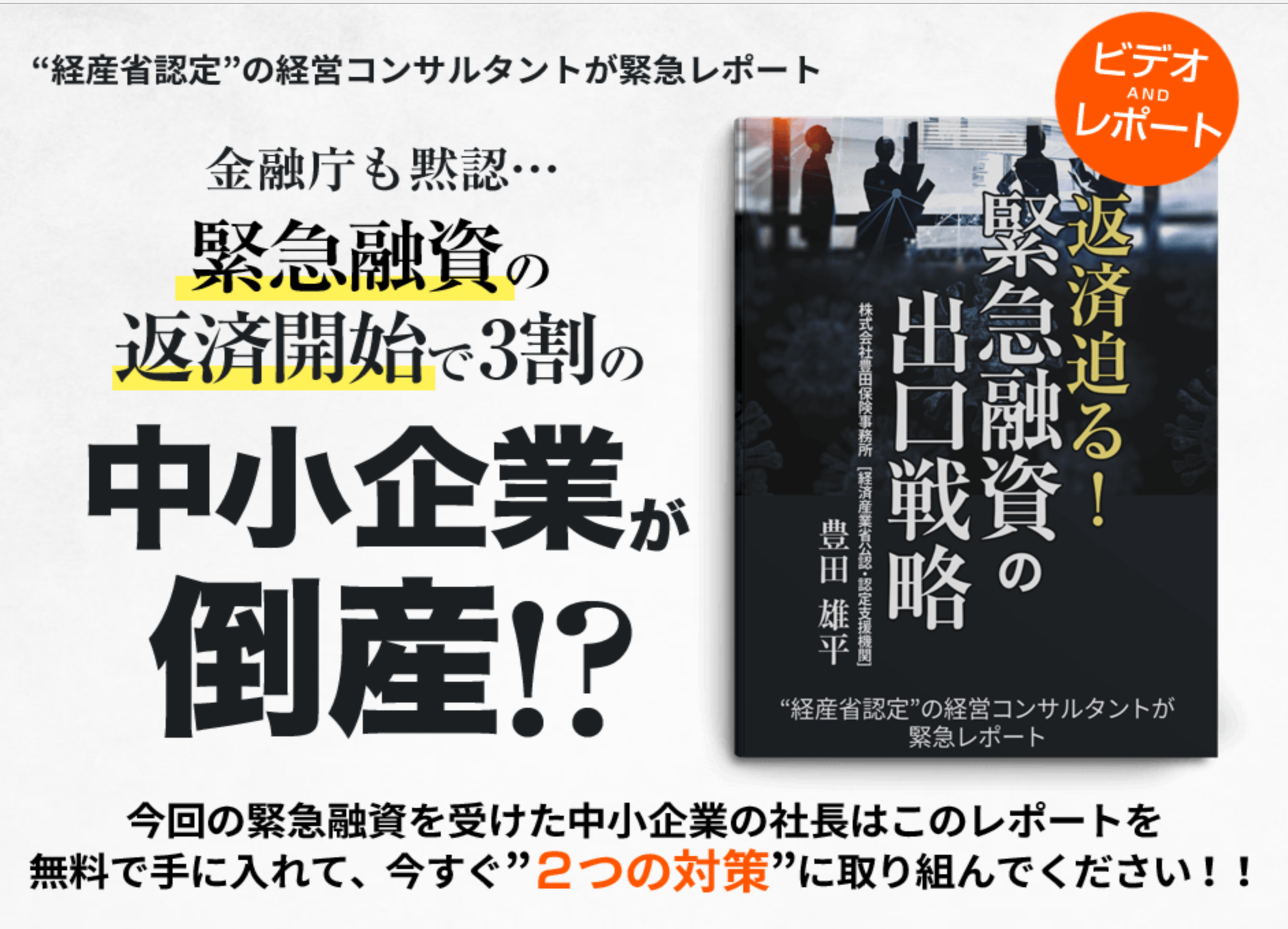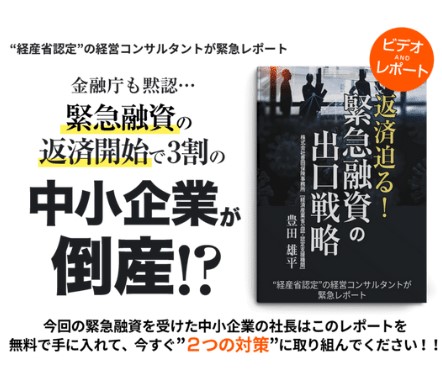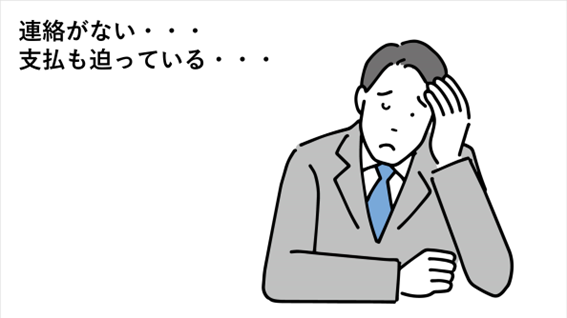
銀行へ融資を申し込んだけど、1カ月たっても連絡がない・・・
これ、珍しいことではありません。
時間だけが経過し、あと2週間もすれば手形の決済がある・・・この時あなたなら、どのような対応を取りますか?
これらは「融資のプロセス」を理解すれば解決できるものです。
気になる方は続きをご覧ください。
目次
まずは店内協議書の作成
中小企業は資金繰りが命です。その資金繰りを支えているのは銀行融資であることは間違いありません。
そこで銀行員はお客様から融資の申し込みを受けた場合、必ず支店長や上長へ報告する必要があります。
そしてその際、「店内協議書」を作成し、資金使途・返済財源・保全について店内で協議することとなっています。これは金融庁の臨店検査の1つにもなっており、重要事項の1つなのです。
そして協議のうえ、支店長からのOKが出れば俗にいう「稟議書」が作成されるわけです。
ではこの流れを理解したうえで、社長はどのように動くべきなのでしょうか?
融資申し込み後2週間経過した時点で行うこと
まずは2週間経過して何も連絡がなければ担当者に確認してください。
担当者も人間ですので、申し込み依頼を忘れている場合もありますし、店内協議書を作成することが億劫で案件にすら挙げていない・・・そんなこともあるからです。
そのため、1ヵ月も待つのではなく、2週間経過した後も連絡がなければ担当者へ連絡を取ることをお勧めします。
その際、仮に融資の申し込みを断られた場合、必ずなぜダメだったのか?この理由を聞くことも重要です。
1つは今後の改善点となるからということと、もう1つは担当者が「嘘」をついている可能性もあるからです。
支店長や上長へ確認してみる
なんだか嘘をつかれてる気がする・・・
そんな嫌な予感がした場合、念のため支店長や上長へ確認を取ることも1つです。
確認方法は、「〇月〇日に担当の○○さんへ融資申し込みをしましたが、案件として挙がっていますか?」と聞いてみることです。
その際、感情的にならずに備忘録をつけて冷静に対処することを忘れないようにしてください。
支店絡みで隠ぺいしようとしている場合などは金融庁へクレームをつけるのも手です。
なぜなら融資申し込みを受けた際、店内協議書を作成することは必須であり、このことは金融庁の臨店検査の重要事項の1つであるからです。
担当行員に店内協議書・稟議書を作成させるコツ
銀行員が店内協議書や稟議書を作成する際、最も重視するポイントは「資金使途」・「返済財源」・「保全」です。
資金使途とはお金の使い途のこと。運転資金?設備資金?何に使うの?ということですね。
返済財源とは読んで字のごとくどのようにして返済していくか?売上で返済するのか?利益で返済するのか?これは借入形態で変わってきます。
保全とは担保のことです。要は返済が難しくなった場合の保険ですね。
最低でもこの3つは明確に答えることが出来なければ銀行員も貸したくても貸せない、案件として挙げられない・・・このように捉えてください。
あなたがお金を貸す場合でも、この3つを明確に答えられない人にお金を貸すか?という点で一度自らに矢を向けてみるといいでしょう。きっと、貸すことはないでしょうから。
最後に普段から担当の銀行員とコミュニケーションを図り、現状報告と今後の見通しについて共有しておけば、今回挙げたような融資申し込みをしたのに音沙汰がない・・・こんなことも起こらないでしょう。
普段からのコミュニケーション、そして社長自身が「資金使途」・「返済財源」・「保全」について明確に回答できるかが非常に重要になってくるということなのです。