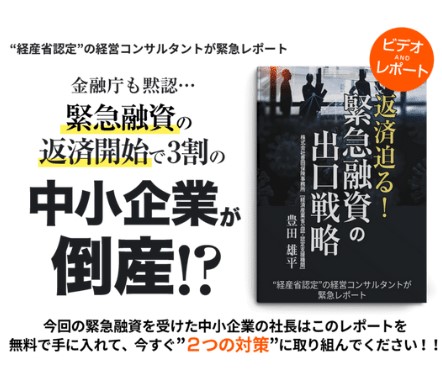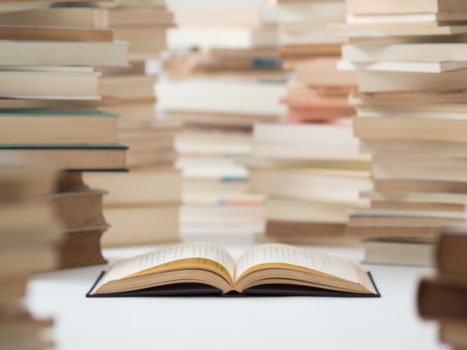
一次評価の合計点数は129点です。しかし、融資を受けられるのは要注意先以上となります。(27点以上)
すなわち銀行の格付けでは、格付けの点数が27点以上にならないと融資は受けられないことになっています。しかもこれは表面で見た点数でなく、「実態」で見た点数です。
目次
決算書の「実態」で見るとは!?
「実態」とは、貸借対照表の資産の部を時価に置き換えることを言います。
特に土地や有価証券は含み損が出ていることが多いため、注意が必要です。
銀行員は不明点があればその会社に確認しますが聞いても最終的に不明点が残ると、それはマイナス評価になります。
銀行員からの質問にはうそをつかないことが大切です。それでも、馬鹿正直に言いすぎると命取りになるケースもあります。
特に貸付金のお金の使い道はやんわりと話したほうが良いでしょう。
また売掛金や在庫は、銀行からすると事業継続の生命線と捉えるため、正確に伝えしないといけません。
説明しきれないといい加減な会社と見なされ、今後の資金調達に影響を及ぼす可能性が出てきます。
格付けは安全性の項目(34点)と債務償還能力の項目(55点)の比重が高い
一次評価の合計点数(129点)から考える比率の高い項目は安全性と債務償還能力です。
債務償還能力では損益計算書の経常利益、安全性の項目では純資産額の合計で判断されます。そのため、経常利益と純資産額の合計が大事であると理解してください。
一次評価の点数が高い指標
自己資本比率(10点)ギヤリング比率(10点)自己資本額(15点)債務償還年数(20点)インタレスト・カバレッジレシオ(15点)償却前営業利益(20点)
一次評価ではこれら6つの指標が高得点になっています。
一次評価で重要な勘定科目
一次評価で重要な勘定科目が3つあります。
①純資産額合計 ②営業利益 ③経常利益です。
一次評価ではこの3つが重要です。なぜならば、一次評価の点数付けでこの3つの勘定科目が関連しないものは13項目の内4つしかないからです。
「流動比率」「収益フロー」「税引き後当期純利益」「売上高」の4つがそれです。
この4つの項目以外は必ず財務指標の計算公式の一部に「経常利益」「営業利益」「純資産額合計」が入ります。
従って、直近の損益計算書で抜群の経常利益を叩き出し、尚且つ、減価償却も行っているのであれば、銀行は高い評価をしてくれることになります。
つまり、経常利益を上げるにはどうしたらいいのか?を改善策として考えます。
そのためには、収益の源泉となる売上を増やし、粗利を適正に確保することです。そうすれば自ずと営業利益や経常利益も増えることになります。