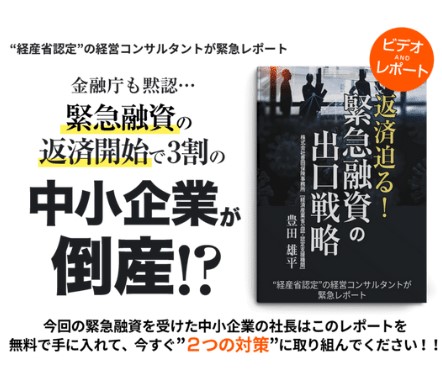銀行の格付け(自己査定)は3つの評価で行います。
一時評価では決算書の資産の項目をかなり詳細に精査し13項目で点数付けを行います。
そこに二次評価を加算し、一度格付けのランクを算出します。
そこから三事評価で修正をかけるという流れです。
まずは決算書を分析する一時評価から見ていきましょう。1次評価では大枠4つの項目に分けて点数を付けます。
それが①安全性・②収益性・③成長性・④債務償還能力の4つです。
その中から決算書の資産の項目を詳細に精査し、さらに13項目で点数付けをします。
まずは大枠の4つの項目について解説していきます。
目次
①安全性の項目
安全背の項目に関することは、貸借対照表の財務指標になります。
資産の格勘定科目の精査をして、実質純資産額を算出したうえで、「自己資本比率」「ギヤリング比率」「流動比率」「固定長期適合率」これら4つの点数付けを行います。
②収益性の項目
収益性の項目背は、3年分の決算書を比較し、税引き後当期純利益が3期連続黒字なのか、2期連続で黒字なのか、といったところを見ます。
このように絶えず利益が計上されているのか?という所を見ています。
前述した「減価償却をしない」という方法をとっても無駄で、銀行員は減価償却をしたところで引き直しをして判断しています。
この収益性の項目は3つの項目しかありませんが、各項目とも5点満点でほとんど格付けに影響を与えません。
銀行員の手を煩わさせて心証を悪くするより、正直に減価償却を行ったほうが良いのです。
③成長性の項目
ここでは経常利益の増加率・売上・純資産の額を見ます。
経常利益は対前年でどの程度増加しているのか?
また純資産額や売上は規模の大きさを判断するために見ます。
どんなに自己資本比率が高くても、売上が少ないとなかなか点数を稼げません。
規模が大きい企業、例えば売上が30億以上、資産の額は15億以上、自己資本比率が50%程度だと点数が高くなります。
④債務償還能力の項目
債務償還能力の項目では、インタレスト・カバレッジレシオで利息の支払い能力を確認し、債務償還年数で長期借入金の元金支払い能力を見ます。
また、融資先のキャッシュフローを見るために償却前営業利益も確認します。
銀行としては、「貸した金は必ず返せ」が原則ですので、この項目は4つの項目の中でもかなり点数が高く設定されています。
言い換えればこの項目で点数が取れなければ、上のランクには行けないということです。
これら大枠4つの項目で129点です。
格付けは200点満点ですので、いかに1次評価が大事であるかが分かるはずです。
2次評価の定性評価は71点と3割程度ありますが、ほとんど見られていないことは何度もお伝えしてきました。
信金・規模の小さい地銀が見ているかどうか?というレベルです。
従って業績が良いところは自ずと良い評価が下され、業績が悪ければ悪い評価が付くことになります。
銀行格付け完全ガイド②へつづく・・・