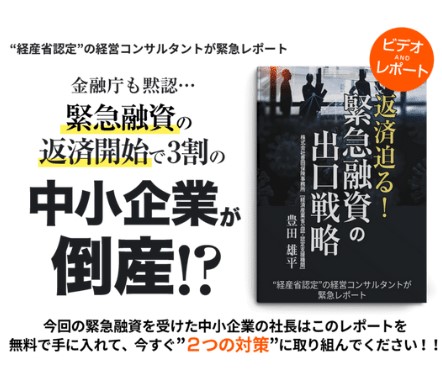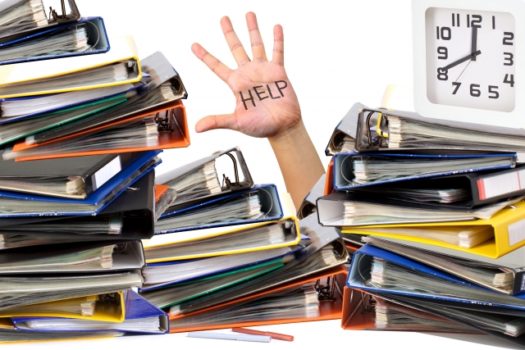
今回も前回に引き続き、銀行の格付けのについてお伝えします。テーマは「よくある銀行格付けの勘違い」です。
この勘違いについて6つの項目に分けてお伝えしていきますが、今回はその中の①~③までの項目をお伝えしていきます。
内容のほとんどが今まで聞かれてこられたものと真逆のことばかりです。
是非項目ごとの解説をご覧になっていただき、こられの勘違いを理解下さい。そして、あるべき姿の銀行の格付け対策を身に付けて下さい。
目次
1.銀行の格付けは融資を受けるための道具ではない!?
銀行の格付けについて時間をかけてお伝えさせていただいている中で、銀行の格付けは融資を受けるための道具ではないということはさんざんお伝えしてきました。
毎回、この記事をご覧いただいている方は銀行の格付け=会社の定期健康診断であるということはご承知のことだと思います。
勘定科目を変えたところで簡単に格付けが上がるかと言えば、上がらないことがほとんどです。下の「定量評価の項目別配転イメージ」をご覧ください。
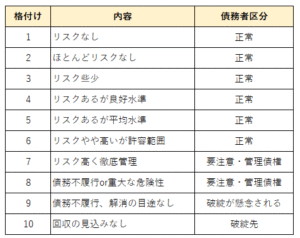
上から①~⑥がいわゆる「正常先」で、銀行からお金を借りるのにそんなに苦労しない先です。ちなみに、各①~⑥のスコアリングの評点は・・・
①リスクなし・・・116点以上(上場企業のみ)
②ほとんどリスクなし・・・103点~115点(上場企業のみ)
③リスク些少・・・82点~102点(年商規模が100億を超えるような企業)
④リスクはあるが良好水準・・・65点~81点(地場の優良な中小企業)
⑤リスクはあるが平均水準・・・52点~64点(ほとんどの中小企業がココ)
⑥リスクはやや高いが許容範囲・・・32点~51点(ほとんどの中小企業がココ)
このスコアリングで60点以上を獲得できるようになると、多くの銀行が無担保で融資したい会社と評価してくれます。
反対に60点未満だと信用保証協会付き融資でお金を貸したいと要請をしてきます。
⑦の要注意先は27点からですが、仮にこのランクの会社が60点まで点数を上げようとするならば、かなりの粉飾が必要でしょう。
売上を2~3割上げ、減価償却を行ったうえで経常利益と営業利益を大きくプラスにし、赤字から黒字に転換させなければなりません。
このようなことができるかと言えば、当然無理でしょう。
仮に勘定科目を多少いじったとして点数が大きく上がるかと言えば、まず上がりません。
従って、中途半端に勘定科目を変えることはやめた方がいいでしょう。
直近3年で何点獲得できていたのか?そしてどこに問題があるのか?ということを把握しながら管理会計の目線で取り組むことが大切です。
2.決算書の勘定科目の移動をしても格付けの評価に大きな影響を与えない!!
仮に点数を上げるために決算書の勘定科目を移動させたとしても評価にほとんど影響を与えません。
例えば正常先の下の要注意先は点数でいうと27点です。
この要注意先から無担保・プロパー融資の入り口である60点を目指すとなると、33点あげることが必要になってきます。
これは、勘定科目を移動させただけでは到底不可能な数字です。
また、勘定科目を操作して27点から32点の正常先に移行したとしても、保証協会付き融資での対応になることはほとんど変わりません。
3.ランクが正常先の6から5へ変わったらどうなる!?
答えから言うと、対応はほとんど変わりません。
先ほどもお伝えしましたが、格付けのランクが要注意先の7から正常先の6や5にランクアップしたとしても、融資商品がプロパーでの対応になるようなことは全くないとは言えないにしろ、ほとんどありません。
担保を設定し、2期連続で経常利益や営業利益が赤字になっていない。
繰越欠損金もなく、債務超過になっていない。
こんな状態であれば、格付けランクが5の50点であっても、プロパー融資が出る可能性もあります。
正真正銘の無担保融資を引き出したいのであれば、60点を超えないとなかなか実現しません。
理想的なのは、正常先の6つのランクのうち4番目、点数が65点です。
但しこれは、自己資本比率が30%を超える会社でないと難しいです。
なので過度の節税や計画性のない税金の繰り延べは好ましくないことは言うまでもないでしょう。
次回へ続く